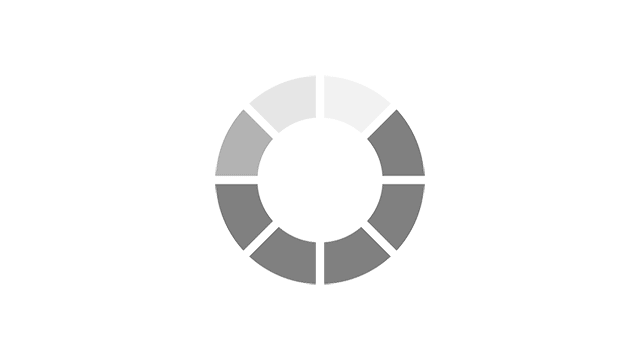
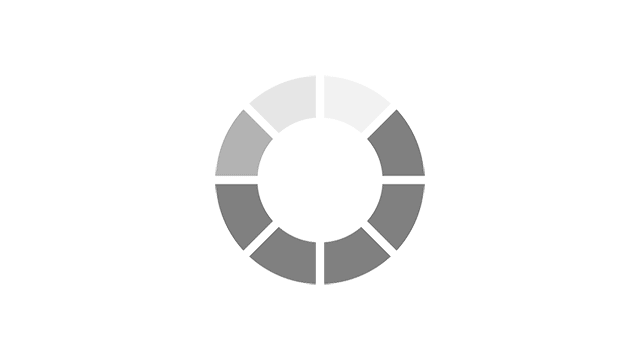
取締役会の監督体制
取締役会は、気候変動対策をサステナビリティの重要課題と位置付け、四半期ごとに取り組みの進捗状況をレビューしています。また、アステラス・サステナビリティ部門は、気候変動対策を含むサステナビリティ関連の取り組みの進捗状況を毎年度取締役会に年次報告書として提出し、モニタリングの一助としています。取締役会は、このモニタリングプロセスを通じて、経営の有効性を監督しています。
執行体制
アステラスは、サステナビリティを重要課題と認識し、業績評価指標(KPI)を設定・モニタリングしています。気候変動対策については、2030年までの達成を目指す温室効果ガス排出削減目標とKPIを通じて進捗状況を評価しています。再生可能エネルギーの導入も、進捗状況を測る上で重要な指標です。サステナビリティ長を委員長とし、Chief Strategy Officer(CStO)直轄のサステナビリティコミッティが、環境行動計画を策定・運用しています。コミッティは、アステラスの環境行動計画を5年ごとに見直し、その妥当性を維持し、必要に応じて改善策を提案します。さらに、温室効果ガス削減に向けた長期計画やTCFD(気候変動関連財務情報開示)への対応状況も評価します。
サステナビリティ目標の役員報酬の業績評価指標への組み込みについては、統合報告書をご覧ください。
アステラスは、社会と当社事業にとって最も重要な課題を特定し、優先順位を付けるマテリアリティアセスメントを実施し、サステナビリティへの取り組みの指針としています。2022年3月期に見直しを行ったアステラスのマテリアリティマトリックスでは、「気候変動とエネルギー」が社会とアステラスの2つの観点から、「非常に重要」と認識されました。
アステラスの環境行動計画は、環境安全衛生ガイドラインの主要項目に関する短期および中期の活動目標を定めています。アステラスは、前年度における進捗状況と状況をレビューし、その結果を次年度の行動計画に反映させることで、行動計画をローリングで更新しています。この計画では、環境負荷の低減と、企業価値の保全に向けた潜在的なリスクの低減に向けた誠実な取り組みを示しています。
気候変動に関しては、社内に情報開示に関する部門横断チームを設置し、シナリオ分析を実施しています。気候変動は1.5℃シナリオで移行リスク、4℃シナリオで物理的リスクが顕在化するという想定の下、アステラスの事業に関する気候変動のリスクと機会を分析しました。分析対象期間は、短期(3年)、中期(10年)、長期(20~30年)です。2021年度からは、毎年、気候関連リスクと機会の分析を実施しています。2024年度には、アステラスの主要拠点およびバリューチェーンにおける物理的リスク分析を実施しました。分析結果は、サステナビリティコミッティでレビューされました。
| 気候変動によるリスク | 潜在的な影響 | 財務への影響 | 影響を受ける期間 | 当社のレジリエンス |
|---|---|---|---|---|
| 移行リスク(1.5℃シナリオで顕在化するリスク) | ||||
| 政策と法 | ||||
| GHG排出価格の上昇(炭素税の支払いによるコスト上昇) | 再生可能エネルギーの導入が進んでいない事業場に対して炭素税の支払いがコストとして上乗せされる可能性がある。 | 2030年度に1トンあたり100ドルの炭素税を想定すると11億円 |
中期~長期 | 事業所で消費する電力の一部は、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用して自家発電されている。 |
| 購入した製品・サービス (スコープ 3 カテゴリ 1) は、炭素税の対象となる可能性があり、調達価格に追加されると負担が増加する。 | 2030年度に1トンあたり100ドルの炭素税を想定すると100億円 | 中期~長期 | スコープ3 カテゴリー1:原材料の使用最適化に取り組む。サプライチェーンのサステナビリティロードマップを策定し、購入製品のCO2排出量データを分析し、排出量削減を優先的に進める。 |
|
| GHG排出規制に伴う既存施設の陳腐化、減損処理 | 環境規制の強化により、設備の廃棄を求められる可能性がある。 フロンガスを用いた冷凍設備を有している。化石燃料を使用する車両は、2035年以降一部の国で利用できなくなる可能性がある。 |
影響は軽微 | 中期~長期 | 廃棄を迫られている既存設備・資産はない。フロンガスについては、法令を遵守し、適切な措置を講じている。 2030年以降は、自動車の進化(内燃機関から電気モーター・EV、燃料電池へのシフト)への対応が求められる。営業車両やトラックのEV化、輸送手段のモーダルシフトは、事業運営に影響を及ぼす。 |
| テクノロジー | ||||
| 低排出技術に移行するためのコスト | 低排出設備への投資に伴いコストが発生する。 | 12億円 当社の気候変動投資額から推計 |
短期~長期 | 炭素税負担を軽減するため、効率的なプロジェクトを選択し、投資する。 太陽光パネル発電など比較的規模が大きいプロジェクトについては、電力購入契約など、投資以外の手段を検討する。 |
| 市場 | ||||
| エネルギーコスト・原材料コストの上昇 | エネルギーあるいは原材料の価格上昇がコスト上昇につながる。インフレはコスト上昇を悪化させる。 | 電力1kWhあたり10円の値上げで、費用負担は20億円増加する。 | 短期~長期 | 今後、規制変更に伴う事業所における電力・エネルギー消費コストの増加は課題となるが、気候変動による医薬品製造原料コストの大幅な上昇は想定していない。 |
| 物理リスク(4℃シナリオで顕在化するリスク) | ||||
| 急性的 | ||||
| 洪水その他の急性的な極端な気象 | 洪水などにより自社事業場の操業が停止する。 サプライチェーンが機能しなくなる。 |
5億円 |
短期~長期 | 富山技術センターの浸水対策は以下の内容からなり、投資額は5億円と見積もられた。 |
| 慢性的 | ||||
降水パターンの変化 |
渇水による自社工場およびサプライチェーンの操業に影響がおよび、製品出荷の遅延が発生する。 |
影響は軽微 | 短期~長期 | IPCC AR6 SPM SSP3-7.0シナリオによれば、2050年の世界全体の海面上昇は1900年と比較して0.5m未満であり、このレベルの変化は事業に重大な影響を与えない。 降水パターンの変化は、当社の事業に重大な影響は想定されない。 |
| 気候変動による機会 | 財務への潜在的な影響 | 影響を受ける期間 | 当社の対応 | |
| 資源効率 | 効率的な生産および流通プロセスの使用 |
運営コストの削減 | 短期~長期 | 感染症のパンデミックや地震、風水害などの自然災害時においても医薬品の安定供給を維持するため、国内に3つの物流センターを運営している。 ヨーロッパ各国、アメリカでは、製薬メーカー複数社が共同利用する倉庫を使用し、流通プロセスの効率化を図っている。 研究・生産サイトの空調排熱を回収し、給気の加温に利用し熱利用効率を高めている。 |
| エネルギー源 | より低排出のエネルギー源の使用 | 炭素費用の変化に対する感度低下 | 短期~長期 | ボイラー燃料を液体燃料から気体燃料に変更している。 営業車両のハイブリッド車および電気自動車の導入を推進している。 アイルランド・ケリー工場で風力発電およびバイオマスボイラーの利用に取り組んでいる。 |
| 製品、サービスと市場 | ・新製品またはサービスの開発 |
変化するニーズに対応し、収益の増加 | 短期~長期 | 気温変化による感染症蔓延地域の拡大や、薬剤耐性問題により想定される感染症治療薬のニーズに対して、解決策のひとつとなり得る人工バクテリオファージの創出に向け大学の研究講座と提携している。 気候パターンの変化により疾患の蔓延地域、罹患率、重症化率が変化する可能性がある。心疾患、呼吸器疾患なども増加の可能性がある。 |
1.5℃シナリオ:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)、 IPCC特別報告書 “Global Warming of 1.5℃” 、国際エネルギー機関(IEA)”Net Zero by 2050”を参照した。温室効果ガス排出の大幅な削減が目指され、カーボンプライスの導入、EVの普及などを想定した。
4℃シナリオ: IPCCが2021年8月にリリースした第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約(SPM)のSSP3-7.0を参照した。極端な気象として、高温、大雨、干ばつなどの頻度増加を想定した。
気候変動の物理的リスクの地理的分析
IPCC報告書[1]では、気候変動による異常気象の増加が指摘されています。しかしながら、脱炭素社会への移行がどのように進むかについては不確実性が高く、アステラスの事業への将来的な影響を予測することは困難です。アステラスは、自社事業拠点、製造委託先拠点、物流拠点を含むバリューチェーンにおける物理的リスク(洪水、風力、山火事、熱波)の影響についてシナリオ分析を実施しました。
評価対象は、アステラスのオフィス、製造施設、研究センター、そしてバリューチェーン拠点です。評価対象となった拠点のほとんどは、東アジア、北米、欧州にあります。短期、中期、長期の定義はリスク機会分析における定義と同じで、長期はアステラスのネットゼロ目標年(2050年)に相当します。参照された気候シナリオは、産業革命以降の世界の平均気温上昇が2℃未満に抑えられるシナリオ(SSP1-RCP2.6)、2~3℃上昇するシナリオ(SSP2-RCP4.5)、4℃を超えるシナリオ(SSP5-RCP8.5)の3つです。
参照
[1] Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report (IPCC AR6) Synthesis Report – Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
リスクマトリックス分析の結果
リスクマトリックス分析において、アステラスの施設の中で最もリスクが高いのは瀋陽工場でした。4℃シナリオでは、2050年における洪水、熱波、降水リスクの増大が潜在的な課題として検出されました。
注: 物理的リスクの影響は、各サイトが 90 メートルのグリッド解像度で位置する場所に基づいて分析されたため、現在導入されているリスク軽減策は考慮されていません。そのため、実際の影響はここで推定される損失と異なる可能性があります。
現在のリスクと、>4°Cシナリオにおける現在と将来(2050年)のリスク変化

リスクスコアは、各ハザードがもたらす平均リスクを正規化した推定値。4℃シナリオにおいて、ハザードの種類に応じて1~3つの指標を用いて算出される。例えば、降水リスクは100年に1度発生する事象における1日の最大降水量を指し、山火事リスクは年間の山火事発生確率を指す。
アステラスに影響を及ぼす可能性のある主なリスク
降水
本分析では、全地点において豪雨の発生頻度が増加すると予測されています。焼津技術センターの所在地では、4℃シナリオを用いた2020年モデルでは50年に一度の豪雨レベルの降雨量が1日あたり357mm、2050年モデルでは398mmと推定されました。
最もリスクが高い日の最大降水量の変動
| 拠点名 | 国 | >4°C シナリオでの一日最大降水量(ミリメートル) | |||||
| 10年に一度レベル | 50年に一度レベル | ||||||
| 2020モデルのベースライン | 2050 | % 変化 | 2020モデルのベースライン | 2050 | % 変化 | ||
| 焼津技術センター | 日本 | 252 | 279 | 10 | 357 | 398 | 12 |
洪水
富山技術センターの立地は、100年に一度発生する可能性のある最大8.5メートルの洪水の危険性があるとされ、特に懸念されます。高リスク地域における洪水リスク対策を評価し、2050年までに潜在的な洪水リスクへの対応が十分に整っているかを確認する必要があります。
熱波
現在、アステラスにとって熱波は大きなリスクではありません。1~100のスケールで評価した場合、現在の平均リスクは29です。しかし、気温上昇が4℃を超えるシナリオでは、2050年までに熱波リスクが顕在化する可能性があると示唆されています。Astellas Gene Therapies Sanfordの所在地では、2050年には年間最高気温が35℃を超える日数が41日になると推定されています。建物の冷却が不十分な場合、熱波によって 従業員の生産性に影響が生じる可能性があります。
>4℃シナリオで2050年に35℃を超える日数(アステラス拠点)
| 拠点名 | 国 | 年間で35℃を超える日数 | ベースラインからの%変化 |
| Astellas Gene Therapies- Sanford | 米国 | 41 | 78 |
強風
強風は、建物が耐風設計になっていない場合、甚大な被害をもたらす可能性があります。しかしながら、日本には厳格な建築規制があり、建物の立地、高さ、用途に応じて定められた風速荷重に耐えられるよう設計することが義務付けられています。
2050年に100年に1度レベルの突風(風速200 km/h以上)が観測される拠点
| 拠点名 | 国 | 突風 (km/h) |
| 焼津技術センター | 日本 | 232 |
その他
寒冷は現在高いリスク スコアが示されていますが、2050 年までにすべてのサイトでリスクは大幅に低下します。山火事はリスクが示唆されている 3PL (サード・パーティー・ロジスティクス)がありますが、雹/雷雨はいずれの場所においても高いリスクは示されていません。
財務インパクト
アステラスへの財務インパクト評価は、4つの災害(洪水、風、山火事、熱波)について実施されました。洪水、風、山火事については、すべての期間における影響を集計し、確率加重した平均年間損失として評価しました。熱波については、最高気温が35℃を超える日数に基づく生産性損失として評価しました。
>4℃シナリオでは、2050年に洪水、風、熱波、山火事による総財務損失は30億円と推定されています。洪水は直接損失総額(19億7千万円)のほぼ3分の2を占め、そのうち67%は富山技術センターにおける推計値です。富山における洪水による潜在的損失は、すべての災害による直接損失総額の44%を占めています。強風は直接損失総額の1/3(9.9億円)を占めています。建物の損害による損失は強風による直接損失の66%を占めています。財務影響が最も大きい拠点は、台風の頻発地域に位置しています。2050年に気温が4℃を超える場合、熱波はアステラスにとって最も重大な気候災害の一つですが、このリスクによる財務影響は他の災害と比較して限定的です。これは、アステラスのすべての拠点に適切な空調換気システムが設置されており、定期的に更新・メンテナンスされているためです。

富山技術センターは、>4℃シナリオにおいて2050年に洪水の影響により15億円の損失が推計されています。下の棒グラフは、富山を除くアステラス施設における総損失額上位10施設を示しており、強風や洪水がアステラス施設に影響を及ぼすことを示しています。
損失の可能性がある上位10拠点(富山技術センターを除く)

リスクを評価・識別するプロセス
気候変動に伴う移行リスク、物理的リスク、風評リスク/法的リスクなど、各部門におけるリスクは、営業、製薬技術、研究、人事、調達、サステナビリティの各部門から構成されるサステナビリティコミッティによって分析されます。リスクは年に1回定期的にモニタリングされ、リスクが特定されると、その影響度と発生確率を分析しています。
規制のエマージングリスクなど、全社的なリスクについては、ファイナンス、製薬技術、研究、調達、サプライチェーンマネジメント、経営企画、サステナビリティの各部門から構成されるTCFDクロスファンクショナルチーム(環境(E)ワーキンググループ)が分析を行っています。クロスファンクショナルチームは、IPCCなどの機関が提供するシナリオを活用し、気候変動シナリオ分析を実施しています。戦略セクションに記載されている物理的リスクの地理的分析も同チームが実施しています。また、炭素税の負担など、低炭素社会への移行に伴う影響についても分析しています。
上記の組織・シナリオ分析に基づくリスク抽出に加え、事業オペレーションおよびビジネスパートナーベースでリスク抽出を行い、シナリオ分析などで見逃されていたリスクも考慮しています。当社では、事業オペレーションのリスク分析としてEHSアセスメントを、ビジネスパートナーのリスク分析としてTPLM(サードパーティライフサイクルマネジメント)を実施しています。EHSの社内専門家として、サステナビリティ部門は製造拠点や研究施設のEHSアセスメントを定期的に実施しています。EHSアセスメントでは、環境・健康・安全全般を評価し、リスクが発見された場合は是正および予防措置計画(CAPA)の策定を求めます。また、主要なサプライヤーや社内部門に対してもEHSアセスメントを実施しています。TPLMは、ビジネスパートナーとの関係構築における計画、デューデリジェンス、契約、継続的メンテナンス、契約終了など、すべての段階を網羅したリスク軽減のフレームワークです。法務、エシックス&コンプライアンス、調達部門によって、複数のドメインにおけるサプライヤーのリスクに積極的に対処し、軽減するためのグローバルなアプローチが確立されています。EHSも上記リスクドメインの一つであり、環境保護と人的安全が実際に業務環境に実装されていることを確認しています。
リスクを管理するプロセス
気候変動リスクを含むエマージェンシーリスクについては、エスカレーション手順等の対策を整備しています。物理的リスクとしては、台風やハリケーン等が事業所の操業に影響を及ぼす可能性があります。過去の台風やハリケーンによる影響は軽微であり、製品サプライチェーンに支障をきたした事例はありません。製造部門では、製品供給に影響が出ないよう十分な製品在庫を維持しています。移行リスクとしては、気候変動対策による設備廃棄はありませんが、今後の設備更新時にエネルギー効率改善を推進することがコスト増加の要因となる可能性があります。気候変動対策への投資額は集計し、コーポレートウェブサイトで公表しています。
気候変動対策として、温室効果ガス排出量の削減目標が達成されない場合、風評リスクが発生する可能性があります。アステラスのサステナビリティ部門は、温室効果ガス排出量の削減状況のモニタリングを行っています。
EHSアセスメントにおいてリスクが検出された場合には、アステラスサステナビリティ部門が改善提案を提示し、是正措置計画の策定を要請します。サステナビリティ部門は、是正措置計画の進捗状況をフォローアップします。
全社リスクマネジメントへの統合状況
気候関連リスクは、サステナビリティへの影響、リスク、機会の一環として、サステナビリティコミッティで審議されます。その後、グローバルリスク・レジリエンス委員会と共有されます。
継続的かつ効果的なサプライチェーン管理は、継続的なモニタリングの対象となり、グローバルリスク&レジリエンス委員会によって監督されます。詳細については、コーポレートウェブサイトをご覧ください。
ESG 目標を達成できない場合の風評リスクも、企業 リスク管理チームによって監視されます。
指数と目標
気候変動リスクと機会を評価する指標
気候関連リスクと機会の潜在的な財務影響を測定するために、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)、水資源生産性、廃棄物発生量を用いています。温室効果ガス排出量は移行リスクに関連し、温室効果ガス排出削減目標の未達成は炭素税負担の増加や風評リスクの悪化につながるため、重要な指標と位置付けられています。一方で、エネルギー効率の改善による温室効果ガス排出量の削減は機会と捉えることができます。水資源生産性の向上は気候変動による水ストレス増大への対策であり、物理的リスクにも関連しています。廃棄物管理の推進は風評リスクへの対策でもあります。
スコープ1、2、3の排出量実績データ
2024年度のアステラスの事業活動に伴う温室効果ガス排出量(スコープ1+2)は、グローバルで10.8万トンでした。スコープ3排出量は128万トンでした。環境・サステナビリティ(環境への取り組み)については、コーポレートウェブサイトをご覧ください。
気候変動リスクの取組みの目標
温室効果ガス排出量(スコープ1+2,スコープ3)
アステラスは、パリ協定の2℃目標に基づき、2018年にScience Based Targets Initiative (SBTi) の温室効果ガス排出削減行動計画の承認を受けました。5年ごとに見直しが必要となるSBTiの目標を1年前倒しで更新し、パリ協定の1.5℃目標(スコープ1+2)とwell-below 2℃目標(スコープ3)を達成するための新たな削減目標を設定しました。この新たな目標は、Science Based Targetとして承認されました。2023年2月には、事業を通じた温室効果ガス排出量削減を推進し、2050年までにネットゼロを達成することを目指す新たな方針を発表しました。
水資源生産性、売上高当たり廃棄物量
アステラスは、水資源生産性と廃棄物発生量を売上高当たりで毎年算出・公表し、目標達成に向けた進捗状況の分析結果を公表しています。両指標とも、基準年と過去3年間の推移を示しています。環境・サステナビリティ(ESGデータ 環境)については、当社ウェブサイトをご覧ください。
アステラスは、環境と社員の安全衛生(EHS)に対する基本的な姿勢を「環境・安全衛生に関するポリシー」に定め、目指すべき姿を「アステラスEHSガイドライン」に示し、組織的・継続的に取り組んでいます。また、優先的に取り組むべき課題については、「環境・安全衛生行動計画」で中期的な目標を設定して取り組みを進めています。
環境・安全衛生に関するポリシー
環境・安全衛生に関するポリシーは、EHSへの取り組みに対するアステラスの普遍的な姿勢を表しています。このポリシーは、国内外のすべてのグループ会社にも適用されており、すべての活動の基本となります。

行動規範体系
アステラスは、経営理念においてステークホルダーの一つとして環境を位置づけ、環境への責任を誠実に果たすために、アステラスグループ行動基準に基づき具体的な取り組みを行っています。
アステラスEHSガイドライン
「アステラスEHSガイドライン」は、EHSへの取り組みにおいて、アステラスが将来に目指すべき姿を統一の基準として示しています。
ガイドラインではアステラスの目指す姿を定性的に示しており、達成期限も含めた具体的な数値目標は、年度ごとに更新する短期・中期の行動計画で設定していくことにしています。また、製造委託先企業に対しても、アセスメント等を通じてガイドラインに準じた取り組みの協力依頼を行っています。
環境への取り組みに関する基本方針や行動計画は、アステラスが取り組むサステナビリティの重要課題として位置づけられています。さまざまな環境課題への対応や実行計画の策定は、サステナビリティコミッティで議論されます。コミッティメンバーは部門横断でファンクショナルユニット*長レベルの従業員で構成され、審議内容はサステナビリティを管掌する CStO (Chief Strategy Officer) に報告されます。気候変動に関する取り組みおよび高い透明性をもった情報開示は戦略目標の一つとして取締役会の定期的な議題とされ、また気候変動のリスクと機会の評価を含むTCFD提言に沿った開示はサステナビリティ活動の一つとして取締役会に報告されています。
環境に関するリスク管理はファンクショナルユニットのサステナビリティによりモニタリングされ、CStO (Chief Strategy Officer) が定期的に報告を受け、必要な指示を行う体制です。特定されたリスクへの対応は、課題の重要度に応じて代表取締役社長CEOが議長を務めるエグゼクティブ・コミッティ†や取締役会にて協議し、意思決定を行っています。
環境管理システムに関する対応として、国内外の全ての商用生産拠点でISO14001認証を取得し、ヨーロッパ生産拠点では安全管理システムのISO45001認証を取得しています。
*各トップマネジメントに直接レポートするビジ ネス遂行のための組織
†アステラスグループ全体の経営上の重要案件を協議する機関


EHSアセスメント
アステラス全体のEHS活動の状況や事業所の課題を明らかにするため、アステラスEHSガイドラインを指標として、全社EHSアセスメントを行っています。評価後、抽出された課題に対しては、その実施状況を書面によるフォローアップ調査と次年度のアセスメントで確認しています。EHS管理統括部門と現場が意見交換することにより、社会的な要請や現場の問題意識を共有し、アステラスが目指す方向性を常に一致させることも、アセスメントを行う目的のひとつです。また,バリューチェーンにおける生産委託先企業に対しても同じ指標によるアセスメントを行っています。指摘事項があった場合、改善案を提示して是正計画の策定を求めており、是正計画に基づいてその改善状況をフォローアップしています。医薬品の安定供給が確実に行える環境を維持するため、アセスメントを通じてバリューチェーンのリスク管理を継続しています。
製品アセスメント制度
一般に製品を製造、販売、流通、廃棄する際の環境への負荷は、製品設計を行う研究・開発段階でほとんど決定されます。とくに、医薬品の製造・販売には、製品ごとに国の許認可が必要であり、作業の安全性や環境負荷低減の目的といえども、一旦承認を受けた製造方法や包装仕様を変更する場合は、新たに国の許認可が求められ、多くの時間と費用が必要となります。このアセスメント制度アステラスでは、研究開発段階・生産段階・流通・廃棄の各段階において、環境負荷の最小化を確保する努力を義務づける仕組みとして「製品アセスメント制度」を導入しています。この製品アセスメント制度では、以下の項目への対応が検討されています。
製品アセスメントを実施する際には、アセスメントチームが製品開発のために段階的にEHSアセスメントを実施しています。その結果、製品の開発が次の段階に進むことができるかどうかが決まります。具体的には、評価では、環境や従業員の健康と安全に悪影響を与える可能性のある原材料またはプロセスを特定する必要があります。是正措置の進捗状況を評価し、行動計画を評価する必要があります。検討中の対策は、その後の評価段階で評価されます。


教育・研修
EHSの改善活動を進めていくには、すべての社員による正しい理解と自らの役割・責任を認識した取り組みが必要です。そのため、EHSに関する公的資格者の育成、専門的な知識や技能が必要な従事者に対する教育など、さまざまな教育訓練を通じて、能力向上に取り組んでいます。事業所に常駐する工事関係者、原材料の納入事業者、廃棄物の運搬・処理委託事業者に対しても、方針や事業所のルールを説明するとともに、EHSへの協力を要請しています。
| 会社名 | 製造拠点 | 認証取得状況 |
|---|---|---|
| アステラス製薬株式会社 | 高萩技術センター | ISO14001(1998年7月) |
| 焼津技術センター | ISO14001(2000年10月) | |
| 富山県技術センター | ISO14001(2000年3月) | |
| 高岡工場 | ISO14001(2000年11月) | |
| アステラスアイルランドCo.,Ltd. | ダブリン工場 | ISO14001(1997年3月) |
| ISO45001(2020年9月) | ||
| ケリー工場 | ISO14001(2003年12月) ISO45001(2018年12月) ISO46001(2024年9月) ISO50001(2012年4月) |
|
| アステラス製薬(中国)有限公司 | 瀋陽工場 | ISO14001(2001年10月) ISO45001(2025年4月) |